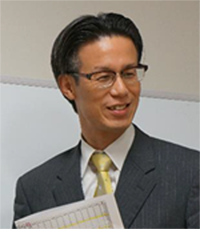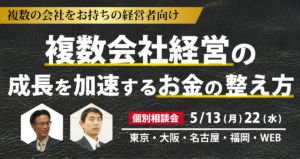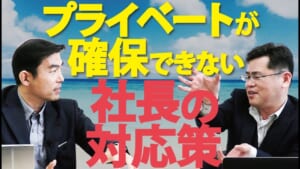変動費と固定費の分け方
私 :「社長、社員に数字を公開しているとのことですが、それを活用していますか。」
社長:「会議で気づいたことは発言するように言っているが、なかなか発言がない。」
私 :「本当に社員の方は、数字を理解していますかね。」
社長:「と言うと。」
私 :「数字の羅列を眺めているだけかもしれません。少し手を動かして、理解してもらいましょう。」
CVP分析という分析方法を、聞いたことはあると思う。これは、損益分岐点分析と言った方が、分かりやすいかもしれない。
CVPの”C”とはコスト(Cost)、
”V”とは販売量(Volume)、
”P” とは利益(Profit) である。
そして、損益分岐点を求める公式は、固定費÷(1-変動費÷売上)となる。最終的には、損益分岐点を求められるようになりたいが、その前に、変動費と固定費に分けることから始まる。
よって、始めから損益分岐点を求めなさいと言うよりも、費用を変動費と固定費に分けなさい、と指示を出した方が良い。
では、変動費と固定とは何であろうか。
変動費とは、売上に比例して増減する費用であり、固定費とは、売上に関係なく一定に発生する費用である。
例えば、売上高と比例して増加する商品仕入は変動費であり、事務所の家賃は固定費となる。
このことを踏まえて自社の費用を、社員で変動費と固定費に分けて欲しい。この作業をしていくと、当然勘定科目の一つ一つの意味を理解しなければならない。ここにも学ぶ機会がある。
そして、その次に勘定科目の横にある数字を見た時に、高いとか安いとか、各自が疑問に思うはずである。これこそが、数字を理解するということである。
つまり、損益分岐点を計算することは大切であるが、受験勉強のように<公式に当てはめて正しい数字を出すことが目的ではない。本来したいことは、損益分岐点を下げ利益を大きくすることであり、経費削減を全社員で取り組むことである。
もし、この費用を100減少させたら、一体売上に換算したらどれだけになるか。そして、それがどのような意味を持っているかを体感することこそが、日々の改善活動の源になる。
是非とも、社内で公開できる範囲の数字で構わないので、全社員で実施して頂き改善活動に繋げていただきたい。必ず、活発な意見交換ができるはずである。
最新のコラムやQ&A、ニュースレターは、無料メルマガ「銀行とのつきあい方」でお届けしております。銀行の動向、資金調達、資金繰り改善、補助金等、経営改善に関する情報を取得いただけます。下記のバナーよりご登録ください!